Contents
哺乳類で出血を伴う生理があるのはサル、人間、犬くらいであり、哺乳類全体から見ると出血が見られるのは珍しいことだとされています。
②発情期
発情期とは、オスを受け入れることができる期間で、排卵が起こる時期でもあります。
期間はおよそ10日間ほどです。
この時期に徐々に出血が治まっていくので、発情期が終わったと思われがちですが、ここでオス犬との接触があると思わぬ妊娠になってしまうことがあるので注意が必要です。
③発情後期
発情後期は、発情期が終わった後のおよそ2カ月間のことで「発情休止期」とも言われています。
この時期には、交配や妊娠の有無にかかわらず、体が妊娠しているのと同じ状態に変化する期間です。
④無発情期
発情後期が終わってから次の発情期までの間の期間になります。
およそ3~4カ月間かけて、発情期~発情休止期にみられた体の変化が元に戻っていくようになります。
避妊手術をする場合には、卵巣や子宮の血管の発達が弱く、出血のリスクの少ないこの「無発情期」に行うことがすすめられています。
犬の生理の症状や出血量
生理(ヒート)中に見られる主な症状は「出血」ですが、それ以外の症状も見られます。
陰部の腫れや、人間と同様に気分の落ち込みやイライラといった精神的な症状が見られることもあります。
また、 症状には周期によっても異なるものがあります。
①発情前期の症状
前述のとおり、この時期にはまず陰部の腫れが見られるようになります。
通常の2~3倍の大きさになることもあるようです。
そして、出血が始まります。
出血量には個体差もありますが、この時期が最も出血量が多い時期となります。
そのため、犬が陰部に違和感を覚えて舐めている様子などが伺えるようになります。
その他にも、ソワソワ・イライラする、オシッコの回数が増える・おもらし、食欲や元気の低下などが見られるようになります。
②発情期の症状
発情期になると、出血量が少なくなっていきます。
交尾に適した時期ともなるため、普段はオス犬を遠ざけるような犬でもオス犬を受け入れやすくなるとも言われています。
また、外陰部に触れる尻尾を横に倒すような反応を示すようにもなります。
これはオス犬を受け入れるサインです。
③発情後期の症状
発情後期では、体が妊娠しているのと同じ状態に変化する期間のため、「偽妊娠」が起こりやすくなります。
偽妊娠によってお乳が出るようになることもあります。
また、この時期にホルモンバランスを崩して、食欲の低下や元気がなくなるなどの症状が見られることもあります。
④無発情期の症状
発情していない時期ですので、この時期には特に症状のない正常期とも言えるでしょう。
人間と犬の生理の違い
これまでご紹介した中でもお分かりかと思いますが、犬の生理(ヒート)は人間の生理とメカニズムが大きく異なります。

出血部位の違い
人間の場合には、分厚くなった子宮内膜が妊娠していない場合に剥がれ落ちることで生理出血が起こります。
一方、犬の場合には外陰部の粘膜が充血することで血液が染み出てきます。
犬の生理出血が起こる部位は、膣や外陰部になるのです。
出血のタイミングの違い
人間の場合は排卵後およそ2週間程度で生理出血が始まるのに対し、犬は排卵前に出血が始まります。
閉経の有無の違い
人間は一定の年齢になると、閉経と言われ生理がなくなります。
しかし犬の場合、高齢になっても生理(ヒート)は続き生涯続きます。
ただし個体差もありますが、出血がほとんど目立たなくなり、一見すると閉経したかのように見える場合もあるようです。
柴犬の生理のケア方法
出血などの症状が見られる犬の生理(ヒート)期間中には、いつもと違ったケアが必要になります。
出血で体や飼育環境が汚れないよう清潔を保ち、ゆっくりと過ごせるようにしてあげましょう。
生理用パンツを着用させる
出血量が多い場合、ベッドや床などが汚れてしまうこともあります。
そんな時には生理用パンツ(マナーパンツ)を着用させておきましょう。
柴犬は体重が6~11kg程度ですので、メーカーによっても異なりますがM~Lサイズ相当のオムツになるでしょう。
犬用のサニタリーショーツや紙パンツなども利用できますが、人間の赤ちゃん用の紙おむつを代用することもできます。
オムツをしておくことで、散歩などでの外出先での思わぬ交尾を防ぐこともできます。
ただし、オムツは蒸れやすく、血液によって細菌も繁殖しやすいため、犬によってはかぶれなどの皮膚トラブルを起こす可能性もあります。
こまめに交換してあげるようにしましょう。
陰部を拭いてあげる
分泌物によって陰部が汚れがちですので、清潔なタオルなどをお湯で濡らしてこまめに拭いてあげると良いでしょう。
ゆっくり休ませてあげる
犬の生理(ヒート)中には、性格が変わってしまったと思うほど、落ち込んだりイライラしてしまうなどの精神的な症状が見られることもあります。
できるだけ普段通りの生活を送らせてあげましょう。





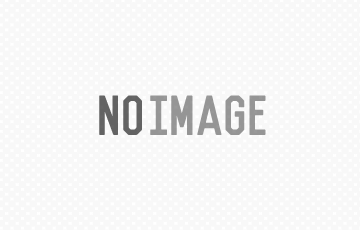



コメントを残す