Contents
また、老化防止のビタミン、関節や筋肉に効果のあるグルコサミンなど、愛犬の体調に合わせて栄養バランスを調整してあげると良いでしょう。
犬がご飯を食べない時の対処
犬がご飯を食べない時、最も多い原因が「犬の気分」によるものだと言われています。
犬にも人間のように好みのご飯があるのです。
もちろん病気や環境の変化によるストレスから食欲が低下していることもあるので見極めが必要になります。
今回は「犬の気分」によってご飯を食べない時に、犬がご飯を食べたくなる3つの対処方法を紹介します。

対処① ご飯に工夫する
実は、犬の味覚は人間の5分の1程しかないと言われています。
そのため、犬はご飯の匂い・舌触り・食感・見た目で嗜好性が分かれると言われています。
つまり、ご飯を食べない時には、匂い・舌触り・食感・見た目の工夫をしてあげることで食欲を誘うことができます。
例えば、いつものドッグフードを温めたりふやかして匂いを出したり、ヨーグルトやすりおろした野菜や果物をトッピングして舌触りや食感を変えてあげたりすることです。
愛犬の好みを探してみると良いでしょう。
対処② 時間内に食べなければ片づける
犬がご飯を食べないからとそのままにしておく置き餌を習慣化してしまうと、犬がいつでも食べられると思って食べなくなることがあります。
ご飯を与えて食べなければ一度下げて、次の食事の時間までは何も与えないようにしてみましょう。
少し可哀そうだと思いますが、そうすることで「今食べなきゃ次まで食べられない!!」と覚えて食べるようになることがあります。
対処③ フードの種類を変える
対処①②を試しても食べない時には、フード自体を変えてみましょう。
ドライフード⇒別の種類のドライフードでも、パウチ、ウエット、手作りなどいろいろ試してみると良いでしょう。
犬のご飯を手作りしてみよう!
愛犬の健康を考えて愛情いっぱいの手作りご飯にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
近年では愛犬のために手作りご飯を与えているという飼い主さんも増えてきました。
しかし中には、手作りしてみたいけれど「手間がかかるのでは」「料理は苦手」と人もいらっしゃるでしょう。
そこで手軽に作れる犬のための簡単ご飯レシピを紹介します。

レシピ① ネバネバ丼ぶり
滋養強壮に効果のある山芋、骨を丈夫にする納豆、抗酸化作用のあるオクラを使ったネバネバ丼ぶりです。
山芋はアレルギーの心配な犬にはおすすめできないので、健康な犬であれば山芋入りを、心配であれば山芋なしで作ってあげましょう。
飼い主さんもだし醤油などで味付けすれば一緒に食べられますよ。
◆材料
- ご飯
- 山芋
- 納豆
- オクラ
- プチトマト(お好みで)
◆作り方
- オクラは茹でて細かく切り、納豆と混ぜる。
- トマトは細かく切り、山芋はすりおろしておく。
- 冷ましたごはんの上に、すりおろした山芋と納豆&オクラを乗せてトマトでトッピング→できあがり!!
レシピ② チーズ鶏ささみ焼き
犬にとっても健康食材鶏ささみと、嗜好性抜群のチーズを使ったレシピです。
彩りににんじんやブロッコリーを添えましょう。
◆材料
- 鶏ささみ
- とろけるチーズ
- 酒 少々
- にんじん
- ブロッコリー
◆作り方
- 鶏ささみ・にんじん・ブロッコリーは一口サイズに切り、一緒に茹でておく。
- 茹でた材料を耐熱皿に移したら、とろけるチーズをのせてオーブンで焼く
- チーズがとろけたらオーブンから出し冷ます⇒できあがり!!
この記事のまとめ
●ご飯の量の計算方法
- 1日に与える餌の量(kcal)=(体重kg×30+70)×係数
●超小型犬~小型犬のご飯
- 小型犬用や犬種別用フードを選ぶこと
- ライフステージ別での回数を参考に、食べ残しや消化不良がないかで回数を調整すること
●中型犬のご飯
- 高タンパクで適度な脂質のフード、さらに「抗酸化成分」や「免疫力維持」タイプのフードがおすすめ
- ライフステージを参考に与え、便の様子を見ながら回数調整を
- 活発な中型犬には、運動量を考慮して量を調整
●大型犬のご飯
- 消化に負担がかからない腸内環境をケアしてくれるフードがおすすめ
- ライフステージ別での回数を参考に、消化状態や胃捻転に配慮した回数調整を
●子犬期に注意すること
- 栄養価の高いフード選ぶこと
- 消化しやすくするため、ぬるま湯でふやかすこと
●成犬期に注意すること
- 肥満に注意し量を与えすぎないようにすること
●シニア期に注意すること
- 食欲の低下
- 基礎代謝の低下に伴う栄養バンスに考慮すること
●犬がご飯を食べない時には
- 温めてトッピングしたり工夫する
- 置き餌をしない
- フードの種類を変えてみる
犬のご飯 正しい回数や量 さいごに
いかがでしたでしょうか。
犬のご飯は、ライフステージや体の大きさ、さらに年齢などによって様々な与え方が必要になります。
少し手間に感じることもあるかもしれませんが、愛犬の健康を守るためには欠かせません。


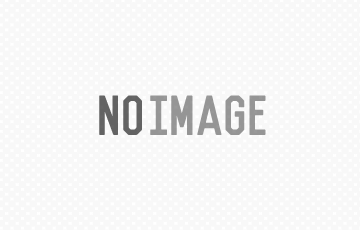






コメントを残す